こんにちは、読売ランド前です。
7月に入り、夏の気配がさらに濃くなってきましたね。
お子さまたちにとっては、期末テストや夏休みが視野に入り、「がんばりどき」と「楽しみ」が交錯する季節です。
今回は、そんな7月にちなんだちょっとした雑学をご紹介します。
ご家庭での会話のきっかけや、学びへの興味を引き出すヒントになれば幸いです。
◆七夕の短冊の色、実は“意味”があるんです
7月といえば七夕。短冊に願い事を書く姿は、昔から変わらない日本の風景です。
でも、あの色とりどりの短冊には「意味」があることをご存知でしょうか?
青(緑)…「徳」=思いやり、やさしさを育む
赤…「礼」=親や先祖、周囲への感謝
黄…「信」=友達や人との信頼関係
白…「義」=正しい行い
紫…「智」=学問や知識の探求
「紫=学び」と知れば、お子さまの勉強運を願って選ぶのも一興です。
意味を知って願いを書くと、ただのイベントも立派な“思考の時間”になります。
◆スイカは野菜?果物?子どもと楽しめる分類クイズ
夏の風物詩、スイカ。実は「野菜」に分類されるのをご存知でしょうか?
これは「草になるか、木になるか」で分ける分類によるもの。
スイカは“草”に実るので野菜、でも果物のように食べられるため「果実的野菜」と呼ばれています。
家庭でこんな話題をふると、
「えー、そうなの?」「じゃあメロンは?トマトは?」と、
子どもたちの好奇心をくすぐるきっかけに。
学習塾ではよく、「知識は“会話”と一緒に記憶される」といいます。
こうした雑談が、意外にも理科や社会の理解につながっていくのです。
◆山開き・海開きに込められた“祈り”
「山開き」や「海開き」も7月の定番行事。
今ではイベント的な印象が強いですが、もともとは自然への畏敬と安全祈願に基づいたものです。
特に山開きは、昔の日本では「神の宿る場所」とされ、入山できる時期が限られていました。
その始まりの日に、感謝と祈りを込めて登ったのが“山開き”。
こうした文化を知ることも、郷土教育や歴史への入り口になるかもしれません。
◆雑学は「学びの芽」を育てるきっかけに
お子さまにとって雑学は、「なんで?」「へぇ!」と感じる入口です。
それが知識への関心や、自ら調べる力へとつながっていきます。
ぜひこの7月は、
「七夕の短冊、何色にする?」「スイカって野菜らしいよ?」
そんな会話を楽しんでみてください。
きっと、夏の学びが少しだけ豊かになるはずです。
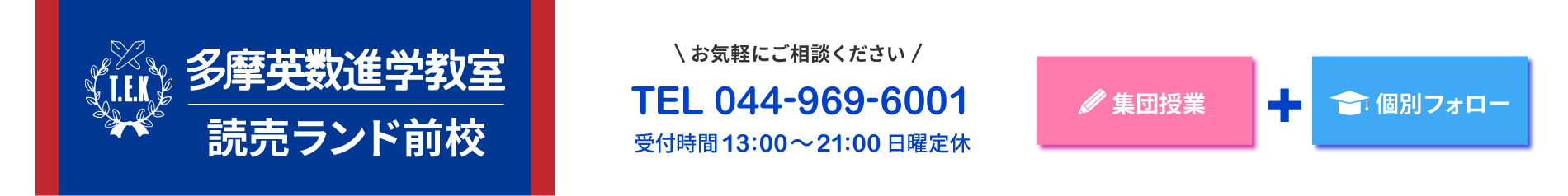



コメント