こんにちは!読売ランド前校です。
11月3日は「文化の日」で祝日ですね!学校がお休みになるこの日、「文化の日って、なんで文化の日っていうんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はこの祝日、私たちの「学習」とも深く関わっている、とても大切な日なんです。
今回は、文化の日の意外な由来と、この日をどう過ごすと将来に役立つかをご紹介します!
1. 文化の日の「2つの」意外な由来!
文化の日が11月3日になったのには、実は2つの大きな理由があります。
理由①:平和への願いが込められた日(戦後)
文化の日は、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として、1948年(昭和23年)に制定されました。
この趣旨の元になったのが、制定のちょうど2年前、1946年(昭和21年)の11月3日に公布された「日本国憲法」です。
戦争を経験した日本が、二度と過ちを繰り返さないよう、平和主義を掲げる新しい憲法が公布された日。その精神を受け継ぎ、平和と文化を大切にする祝日として「文化の日」が生まれました。
理由②:もともと「明治天皇の誕生日」だった(戦前)
実は、11月3日は戦前からずっと祝日でした。それは、明治天皇の誕生日を祝う「天長節(後に明治節)」という祝日だったからです。
戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向もあり、天皇にまつわる祝日は見直されることになりました。しかし、長く親しまれてきたこの日を完全に祝日からなくすのではなく、新しい意味を込めた「文化の日」として引き継がれたという背景もあるのです。
つまり、文化の日は、日本の歴史(明治節)と新しい日本の始まり(日本国憲法)が重なり合って生まれた、特別な一日なのです!
2. 文化の日が「学習」につながる理由
「文化」というと、美術館や音楽をイメージするかもしれません。しかし、文化とは、私たち人間が生み出した「知識」「芸術」「学問」「技術」「生活の知恵」など、すべてを含みます。
皆さんが毎日学ぶ数学、歴史、科学、国語…これらすべてが、先人たちが積み重ねてきた偉大な文化です。
文化の日には、ぜひ以下のことを意識して過ごしてみましょう。
● 知識の吸収
・地域の図書館や美術館・博物館に行ってみる。文化の日には無料開放している施設も多いですよ!
・歴史の偉人たちがどんな発明や発見をしたのか、少し深掘りして調べてみる。
● 創造性の発揮
・普段は読まない分野の本を読んでみる。
・絵を描く、楽器を演奏するなど、自分の「文化」を創造してみる。
文化の日は「学ぶことの楽しさ」や、「自分たちが今学んでいることが、どのように世界を作ってきたのか」を実感できる最高のチャンスです!
まとめ
11月3日「文化の日」は、平和への誓いと、先人たちの歩んできた歴史が込められた日です。
文化の日に、ぜひ一度立ち止まって「文化」とは何かを考えてみましょう。それが、皆さんのこれからの学習をより豊かに、より深いものにしてくれるはずです!
読売ランド前校では、日々の勉強を通じて、皆さんの未来を形作る「文化」や「知識」をしっかり身につけられるようサポートしていきます!
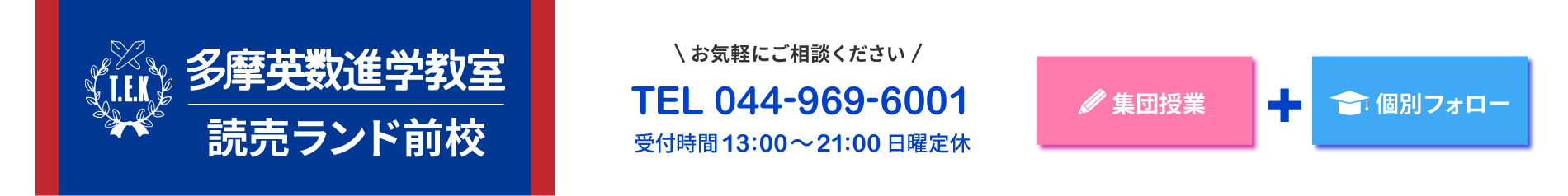



コメント